こんにちはたぬきです。
今回は、自立支援医療(精神通院医療)制度についてお話しします。
自立支援医療(精神通院医療)制度とは
精神的な病気になって、継続した通院が必要な方に対して、
通院の時の支払い額を軽くする(1割にする)ことによって、
自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
精神疾患には統合失調症、うつ病の他、薬物などの急性中毒や依存症、PTSD、パニック障害、知的障がい、発達障がい、認知症、てんかんも含みます。
こういった病気は、比較的長期間通院し、服薬しないといけないことが多いです。療養するため、仕事を休んでいたり、一旦辞める方も多くおられます。そんな中で通院の度に医療費がかかっていくのは、とてもしんどいですよね。そういった負担を軽くするための制度です。
※精神保健福祉手帳や障害年金とは別の制度になります。
制度の対象になる人はどんな人か?
「一定以上の精神疾患の症状があり、継続的に通院する必要がある人」です。
これは、もちろん自己判断ではなく、通院先の主治医が作成する「診断書」によって判断されます。
※自立支援医療には、「身体障がいがあり、その症状を手術等の治療により確実に軽減、除去する効果が期待でき方」も対象ですが、今回のブログでは精神医療についてお話ししています。
どのくらい医療費の負担が軽くなるか
簡単にいうと、1割でOKになります。
例えば、今まで通院すると3割負担で支払っていた方は、医療費が仮に10,000円とすると
今までは、10,000円×30%=3,000円を窓口で支払っていましたが、
これが10%の1,000円で良くなるということです。
また、月に何度も通院しないといけない人には世帯の所得に応じて、月ごとの上限額も設定されています。
※この場合の「世帯」は、同じ健康保険に加入している家族をいいます。所得の区分は、
・「国民健康保険」であれば、世帯内の被保険者全員の所得、
・「国民健康保険以外」であれば、被保険者の所得により認定されます。
さらに「医療費が高額な治療を、長期間にわたり続けなければならない」とされた方(制度上は「重度かつ継続」と言います)は1カ月あたりの負担限度額が低くなっており、
どんなに所得が高くとも月々20,000円が上限になっています。
→ 詳しくはこちら「厚生労働省ー自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」
https://www.mhlw.go.jp/content/001507765.pdf
制度が使える範囲は?
外来での受診、投薬のほか、通所型の施設の利用(デイケアと言ったりします)、訪問看護の費用なども対象です。
適切に継続した治療を行うため、医療機関・薬局・訪問看護ステーションなど実際に利用するところを限定して登録します。
そのため、例えば「通院先が休みだったから、臨時で別のところを受診した」場合は、制度は使えません。また、転院したい場合は変更申請をする必要があります。
入院の費用、病院や診療所以外で個人的に行うカウンセリングなどは対象とはなりません。
今回は、制度の概要についてお話ししました。
次のブログでは、実際の申請方法と使い方をお伝えします。
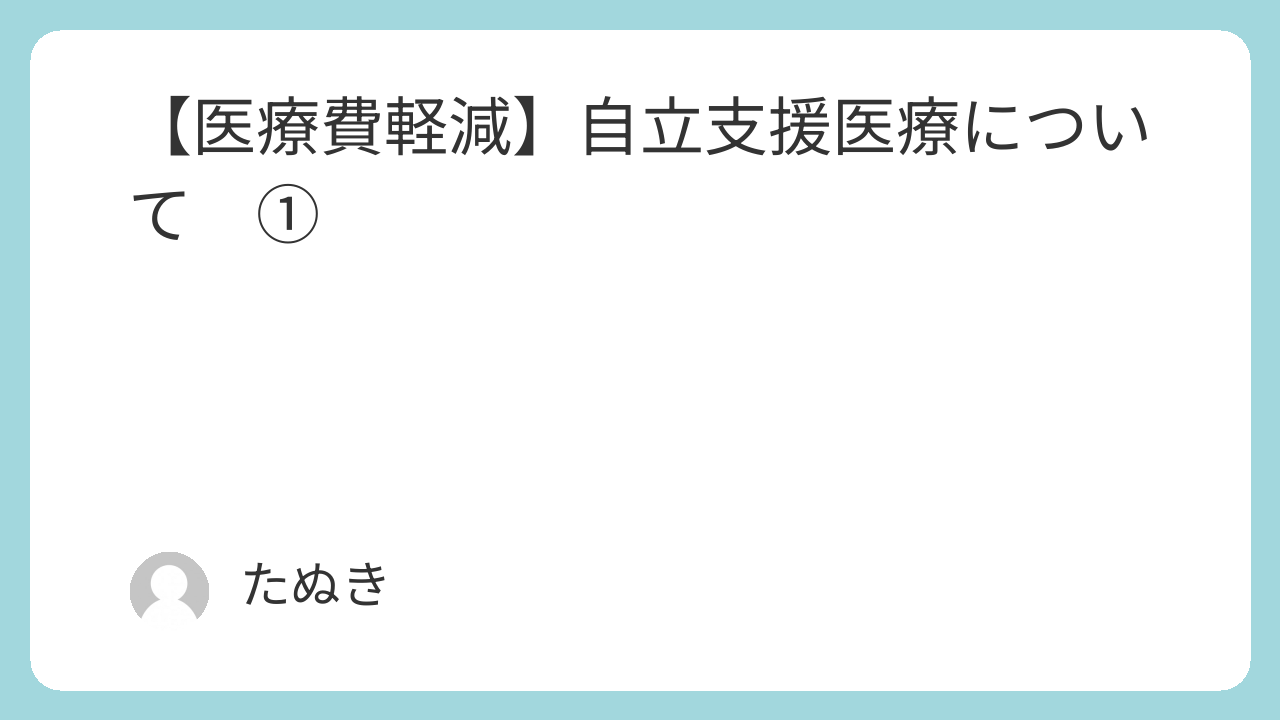
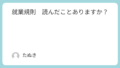
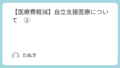
コメント